前回は「ボリンジャーバンド」を紹介しました。ボリンジャーバンドでは標準偏差を用います。パラメーターを2標準偏差に設定すると、統計学上、95%の範囲内で入るであろうと計算されるボリンジャーバンドがローソク足に上下に描かれます。ビジュアル的にはわかりやすいテクニカル分析でした。
ところで、今回紹介するテクニカル分析はボリンジャーバンドに似ているのですが、ボリンジャーバンドとは全く違うモノです。
まずは、下図を見てください。

この図はボリンジャーバンドではありません。でも、ローソク足の上下に2本のラインが描かれていて、ボリンジャーバンドに似ていると思いませんか。
例えば、赤矢印の部分を見てください。現在値がラインに到達すると流れが変わっているのがわかります。ボリンジャーバンドの持つオシレーター系機能とそっくりですよね。
実はこのテクニカル分析は『エンベロープ』と言います。
それでは、エンベロープの解説をしていきましょう。
下図を見てください。
ドル円の日足に移動平均線を描いています。パラメーターは20日を使っています。

移動平均線はトレンドの分析を得意とするテクニカル分析です。特に、移動平均線の上方を現在値が推移している時には堅調な展開が続いていると判断できます。逆に、移動平均線の下方を推移している時には軟調な展開になっていると考えることができました。
ここで、上昇トレンドが続いている場合を例に考えてみたいと思います。
現在値は、もちろん、移動平均線の上方に位置しているのと同時に価格も移動平均線も右肩上がりで推移していきます。
そして、上昇トレンドが続くと、現在値は上昇を続け、移動平均線も現在値を追いかけるように推移していきます。
ところが、上昇が続くほど現在値と移動平均線の距離、すなわち乖離幅に注目すると、その差が開いていくことになります。
でも、未来永劫上昇が続く上昇トレンドはありません。どこかの水準で上昇トレンドも終焉し、上昇が止まります。
そこで、現在値が移動平均線からどれくらい離れたら(乖離したら)流れが変わるのか、そこに規則性はないのかという点に着眼したのが、エンベロープなのです。
上図の赤矢印で示した箇所は、移動平均線から大きく離れた水準から逆の動きになった個所を示しています。
ここからも、永久に乖離幅が拡大していく、つまり、上昇トレンドおよび下落トレンドが永久に続いていくことがないことがわかると思います。つまり、価格は移動平均線を挟んで上方で推移したり、下方瀬で推移したりを繰り返しているのです。
では、移動平均線から1%の乖離したエンベロープを描いています。

緑色の移動平均線から1%離れた水準にエンベロープを描いています。しかし、パラメーターを1%に設定すると、現在値が頻繁にエンベロープを超えてしまうのが確認できます(青矢印)。
そこで、パラメーターとして、1%から2%、3%と調整していきます。

上図は20日の移動平均線(緑線)に移動平均線から±3%離れたエンベロープを描いています。
ここからドル円は20日の移動平均線から±3%以上を超えて上昇ないしは下落する確率は低いと考えることが出来ると同時に、エンベロープに到達したら、『買われ過ぎ』ないしは『売られ過ぎ』と考えることが出来るのです。
ビジュアル的にも捉えやすいテクニカル分析であることがわかります。
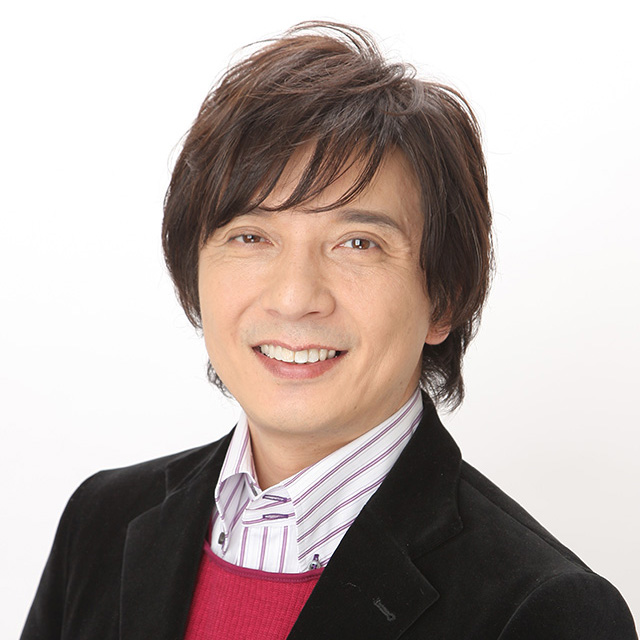
川口 一晃(オフィスKAZ代表取締役)
1986 年銀行系証券会社に入社。銀行系投資顧問や国内投信会社で11年間ファンドマネージャーを務める。
2004年10月に独立してオフィスKAZ 代表取締役に就任。